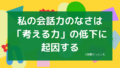※当記事はPRを含む場合があります。
こんにちは。双極性障害の躁鬱くん(@so_utsu_kun)です。今日、Xでフォローさせていただいているあさひなさんから以下のポストがありました。
精神科医をやっていて鬱の話や死にたいという話をたくさん聞かされて自分も引っ張られて鬱にならないかと良く聞かれるのですが、全くないです。これは医師でなくても大事なことですが、自他境界がはっきりしていれば引っ張られることはありません。自分は自分、他人は他人。
— あさひな (@Asahina_sou2) April 12, 2025
精神科医の方々はこの「自他境界」がはっきりしているからこそ精神科医をできるんだな…と単純に関心する一方で
果たして自分はできているだろうか・・・
と考えたところ

全然できてないのでは?
と感じました。
芸能人が炎上している時になぜか自分まで非難されているような暗い気持ちになって引っ張られちゃったり、自分が楽しいことは夫も楽しいはずだと思って趣味の押し付けをして嫌がられたり…とにかく、
自分と他人は別人格であるという認識が薄すぎるのではないだろうか(そのため夫婦関係でも問題が生じやすい)
と思い当たりました。
そこで今回は、自他境界の作り方やトレーニング方法などを調査しました。
そもそも「自他境界(バウンダリー)」とは
自他境界とは、自分と他者や物事との間にある境界線、またはその境界線を意識する機能のことです。自分と他者を区別する心理的な境界線とも呼ばれ、「バウンダリー」とも呼ばれるそうです。
| 定義 | 自分と他者は別のものであるという境目 |
| 機能 | 無意識にできる能力で、周囲の影響に左右されずに他者と関わっていくことを可能にする |
| 問題 | 曖昧になると人間関係に支障をきたしたり、心の不安定さにつながったりする |
赤ちゃんの頃はだれしも自分と母親の存在があいまいで自他境界がない状態と言えます。
そこから心身の成長やたくさんの経験を積み重ねるにつれて、徐々に自分とそれ以外の人は違うのだという感覚を学んでいき、成熟した大人になるころには「自分は自分、他人は他人」という自他境界を身に着けられるのが成長なのでしょう。
ですが、この自他境界が何らかの原因であいまいになってしまうことがあるようです。
自他境界があいまいな人の特徴とその原因
自他境界があいまいな人は、言ってしまえば「自分」と「他人」のあいだに線を引くのが苦手です。
その結果、以下のような特徴が現れることがあるそうです。
- 相手の気分に強く影響される
- NOと言えない、人に嫌われるのが怖い
- 境界線がないから“溶け込む”か“遮断する”か極端になる
- 共依存的な関係に陥りやすい
相手の気分に強く影響される
たとえば、誰かの機嫌が悪いだけで「私が何か悪いことをしたかも」と感じたり、「なんとか元気づけなきゃ」と責任を背負いこみがちです。
他人の感情が、自分の感情のように入り込んできてしまいます。
NOと言えない、人に嫌われるのが怖い
誘われたくない集まりに断れなかったり、頼まれごとを断ると罪悪感を感じてしまう人も多いそうです。
「相手がどう思うか」が第一優先になってしまい、「自分はどうしたいか」が後回しになりがちになる人もいます。
境界線がないから“溶け込む”か“遮断する”か極端になる
人と近づくと「全てをわかってほしい/わかってあげなきゃ」みたいになってしまう一方で、傷ついたときには「もう誰も信じない」とシャットアウトしてしまう。
ゼロか100かの関係性になりやすいです。
共依存的な関係に陥りやすい
恋人や親友、パートナーとの関係で、「相手がいないと自分がわからない」と感じたり、「自分の人生=相手のため」といった状態になることがあります。
自分の輪郭があいまいなぶん、他人と自分の感覚が溶けあってしまいやすいんですね。
自他境界があいまいになる原因
では、なぜ自他境界があいまいになってしまうのでしょうか?
多くの場合、その背景には生育環境や過去の経験が大きく関わっているようです。
- 幼少期の家庭環境(過干渉・無関心)
- 感情を表現するのがタブーとされた環境
- トラウマや対人トラブルの影響
幼少期の家庭環境(過干渉・無関心)
・親が過干渉だった:
たとえば「今日は〇〇ちゃんはこうしなさい」と、子どもの意志を尊重せずに指示・干渉ばかりする親。子どもは「自分の感情より、親の期待に従うほうが安全」と学び、自分の境界線をあいまいにしてしまいます。
・親が無関心・ネグレクト気味だった:
逆に「見捨てられ不安」を強く感じながら育つと、「他人に見捨てられないようにするには、相手の気持ちを優先しなきゃ」と、自他の境界を削ってしまうケースもあるそうです。
感情を表現するのがタブーとされた環境
「泣くな」「怒っちゃダメ」「いつもニコニコしてなさい」
こんなふうに育てられると、自分の感情を表に出すことに罪悪感を抱くようになるようです。
その結果、「自分の本音ってどれだっけ?」とわからなくなり、他人の感情に乗っ取られやすくなってしまいます。
トラウマや対人トラブルの影響
過去にいじめ、モラハラ、DVなどの経験があると、相手の機嫌や言動に過剰に敏感になる場合もあります。
「相手を怒らせないように生きる」というクセがつくと、いつの間にか自分の輪郭が曖昧になっていきます。

ここまで読んで「自分のことだ」と当てはまった人がいるかもしれません。
次に少し私の話をさせてください。
私は自他境界があいまいだけど原因が必ずしも当てはまるわけでもない
先ほど、自他境界があいまいになる原因として「幼少期の家庭環境」や「トラウマ的な体験」が関係していることが多い、という話をしました。
でも、じゃあ自分の場合はどうだったんだろう?と振り返ってみたときに、私の場合は正直そこまで“わかりやすい原因”が思い当たりません。
たしかに、両親の仲はあまり良くなかったし、家の中の空気は多少ギクシャクしていたと思います。でも、自分に向けられた愛情が「過剰」だったとか「極端に不足していた」とは感じていません。
それよりも私の場合は、小さい頃から“人に褒められること”が好きで、それを生きがいとして感じているような節があった気がします。
親や先生に「すごいね」「えらいね」と言われたくて、がんばる。注目してもらえると嬉しい。でも逆に、無視されたり、否定されたりすると、ものすごく不安になる。
その感覚が大人になってからも続いているのかもしれません。
特に「好きな人」には、自分のことを「わかってほしい」「通じ合いたい」という気持ちが強く出てしまいます。
この「わかってほしい」「通じ合いたい」という欲求が強すぎるあまりに、
「相手の気持ちと自分の気持ちの区別がつかない」
「相手の言葉一つで気分が大きく揺れる」
「自分の感情をどう扱っていいのか分からない」
といった状態に、何度もなってるのかもしれないという認識です。
だから私は、自分の自他境界があいまいなのは、必ずしも環境だけのせいじゃなくて、性格や気質によるものもあるのでは?と思います。
実際、私は自他境界の甘さと出現した精神症状を総合して、大学生の頃「境界性パーソナリティー障害の疑い」として診断されていたのですが、何でもかんでも精神科医が「生育歴のせい、家庭環境のせい」と結論付けたがるのには正直うんざりしていました。
上記の診断について精神科医のセオリーとしては間違っていないのだと思いますが、自他境界のあいまいさに関しては生まれ持った性格や気質によって出現することは往々にしてあるのではないでしょうか。
自他境界のあいまいさを直す方法とは
さて、愚痴っても仕方ないのでこれからの人生のために、直し方についても確認したいと思います。
ネット上の情報をいくつか調べて、これは自分にフィットするかなと思ったものをピックアップしてみました。
- 「自分の課題」と「他人の課題」を分ける
- 断る練習をする
- 客観的な目選を持つ
- 自他境界について学べる本で学ぶ
「自分の課題」と「他人の課題」を分ける
アドラー心理学の考え方で、「課題の分離」という概念があるそうです。
これは、「それは誰の課題なのか?」を意識して線引きをすることで、自他の境界をはっきりさせる手法です。
たとえば、友人が不機嫌だったとしても、「その人がどう機嫌をとるかはその人の課題。自分がすべて責任を負う必要はない」と考えるようにします。
この視点を取り入れることで、他人の感情や行動に過剰に巻き込まれにくくなります。
私も実際に読みました。以下の本はかなりわかりやすいです。
断る練習をする
「NO」と言うのが苦手な人は、相手の期待や要求を優先しすぎてしまいがちです。
まずは、小さなことでもいいので「断ってみる」ことを意識してみるのがいいそうです。
たとえば、「今日は疲れているから誘いを断る」「お願いされたけど、いまはできないと伝える」といった行動を、少しずつ実践していきます。
その際、相手に嫌われるかどうかよりも、「自分の本音を尊重できたか」を評価の基準にすることが大切です。
客観的な視点を持つ
感情に飲み込まれて「自他境界があいまいになっているかも!?」と気づくけどどうしたら良いかわからないという時が出てくるかもしれません。
その時は自分と他人を上空から眺めるような第三者の気持ちで状況をとらえてみると良いかもしれません。
これは「自他境界のあいまいさ」にだけ効く手法ではなく、双極症などの精神疾患のうつや躁状態でも客観視できる効果的な手法だと思います。
大学生の時、学科の教授がこの方法のことを「小人飛ばし」と呼んでいました。(自分の分身である小人がいろんなところにいると考えて様々な角度から客観的に物事を見られるようにする)
※出典を調べたのですがこれについては分かりませんでした。
自他境界について学べる本で学ぶ
そのほか、自他境界について学べる本に以下のようなものがありました。
今後、私が実践すること
私は自他境界があいまいなせいで
- 自分が楽しんでいるものを夫も楽しんでほしい
- 自分が腹立ったことを共有して一緒に腹を立ててほしい
とか単純に自立できていない症候群を抱えています。
まずは自分は自分、夫は夫、他の人は他の人という点を区別して考え、人に自分の主張を強く押し付けたりしないで自分の中で完結できる自分になるよう努力していこうと思いました。
皆さんは「自他境界」という言葉知っていましたか?
今回この単語に出会ったことで、もう1歩前に進んで人間として成長していきたいなと思いました。
認知行動療法を試すなら、スマホアプリAwarefy(アウェアファイ)がおすすめ!
「精神疾患のセルフケアをしたいけどどうしたらよいか分からない」のほか、今回の記事で紹介した「自他境界のあいまいさを直す」というテーマについて、認知行動療法が改善の手助けをしてくれるかもしれません。
私自身も、

精神疾患だけどカウンセリングは嫌い・・・
でも病歴も長くなってきたからいい加減自分をコントロールできるようになりたい!
と感じて利用を始めたのがAwarefy(アウェアファイ)というスマホアプリです。
Awarefy(アウェアファイ)は、心理学と最新のAI技術で手軽に認知行動療法が試せます。

詳しい使用感は以下記事を参考にしてください
▶関連:Awarefy(アウェアファイ)無料版の機能と使い方
▶関連:Awarefy(アウェアファイ)をキャンペーンで割引する方法
以下ボタンから当サイト経由で年間プランに登録すると利用料金が20%OFFになるのでぜひチェックしてみてください。
\以下サイト経由なら20%OFF&
7日以内なら全額返金保証付き!/
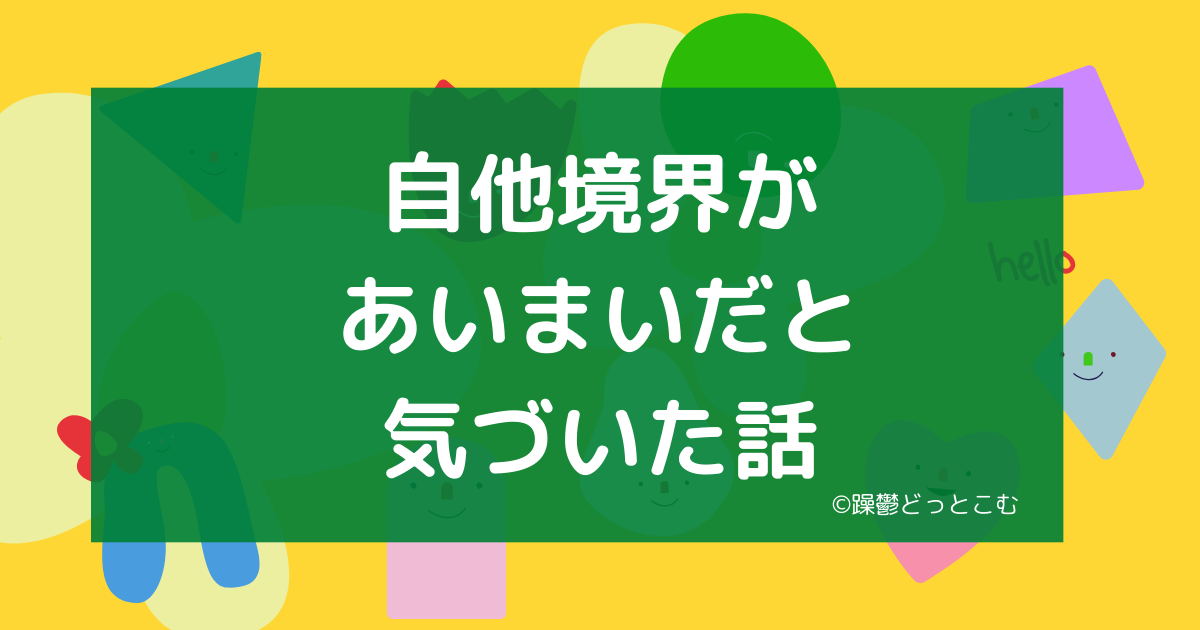
アイキャッチ-160x90.png)